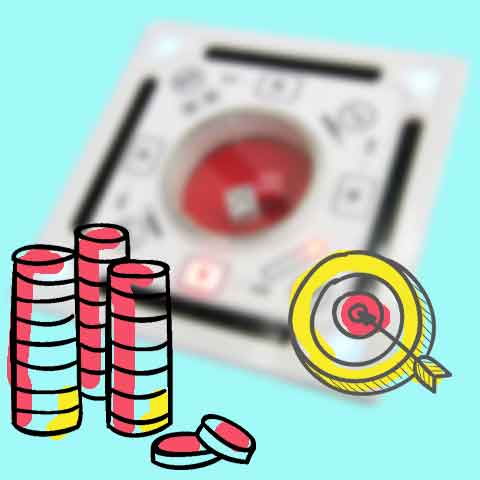彼はたぶん、五歳の誕生日にそれをプレゼントされた。
それは、造りものの二色の花で、上からハンカチーフでおおい、そのハンカチーフを取り除く時にうまくやると、花の色が変わる、という奇術用具だった。
実際には花の色が変わるのではなく、一瞬の内に花の色が変わったように見せるトリックだ。
ツルリとした光沢の絹のハンカチーフを取り除く時に、二色の花の上の部分をハンカチーフと一緒につまみながら外すことで、筒状の上に花開いた装飾がほどこされているネタの下に隠されていた別の色の花びらが現れるのだ。
彼には最初、それがトリックであるとの認識はなかった。
かぶっていた帽子の下の頭髪があらわになっただけのことだろうと思った。
だが、それを人前で演じてみせると、もちろん演じるなんて意識はなかったけれども、多くの人は彼がそれまで見たことのない反応をした。
そしてその反応を前にした彼は、それまで味わったことのない不思議な幸福感の中にいた。
彼はいっぺんで奇術のとりこになった。
マジシャンとしての彼の人生が始まった。
彼の演じた初歩的なトリックに対して人々がみせた反応には理由があり、それをすぐに理解できる程度には彼の知能は発達していた。
後から考えると、その時に理解できた理由だけが、人々の驚愕という反応の根拠とは言い切れないのだが、少なくともうわべの理由は、
・花の色が一瞬に変わるなんて普通はありえない。
・目の前で、そのありえないことが起こった。
からであり、それがありえないことでも何でもないことは、そのネタを知り、それを演じた彼にはわかっていた。
かぶっている帽子を脱ぐだけでは誰も驚かない。
もしも帽子ではなくカツラであったら少しは驚くかも知れない。
さらには、ただカツラを取るのではなく、いったん布で頭部を隠し次の瞬間に布を外すのと同時にカツラを取ってみせれば、皆は喜んでくれる。
このようなカツラの比喩は当時の彼にはできなかったが、それに近いことは充分に思考できた。
二色の造花と絹のハンカチーフという用具に本質があるのではない、と喝破できたことから、実は彼には先天的なマジシャンとしての資質が備わっていたことがうかがい知れる。
重要なのは、グッズではなくロジックなのだ。
十歳になった彼にとってもっとも至福の時間を過ごせる場所はデパートの奇術用具売り場のコーナーだった。
黒いスーツと蝶ネクタイ、胸のポケットから白いハンカチーフを半分のぞかせている、売り場にいるマジシャンが次々と見せる魔法の数々は彼をとりこにした。
そこで彼が買い物をすることはほとんどなかったが、何時間も飽きもせず、マジシャンの手元を注視し、マジシャンの口上を聞き続けた。
トリックがどうなっているのだろうと考えることもよくあったが、不思議な現象を目の前にすることそれ自体がとても楽しいことだった。
当時の彼はすでに、マジシャンが起こす魔法のすべてに何らかのネタが存在することを充分に知っていたにもかかわらず、いつも驚き、現象を目前にした時に自分を包んでくれる不思議な感覚を何度も味わった。
その感覚、センスオブワンダーに浸ることが心地よかったのだ。
休日に一人ででも奇術用具売り場のコーナーに行き、憧れのマジシャンとも口をきくようになってから何度か一般の客の前で奇術を演じることがあった。
目的は客に奇術用具を売ることなので、ショーケースの中に陳列されている用具を使ってのパフォーマンスだ。
いくつかの奇術は完璧に身に付けていた。
用具を手にすることは初めてであっても、ネタの基本がわかっている奇術、それまでに経験のある奇術と同様のロジックで構成されている奇術のいくつかは演じることができたのだ。
しかし中には、当然のようにネタのわからない奇術もたくさんあったし、ネタは理解しているのにうまく演じることができない奇術もあった。
ロジックを把握しているのに演じることのできない奇術があるのは、彼にはまだ足りないものがあったからであり、それはその奇術に必要なテクニック、ハンドパフォーマンスだった。
用具の造りが簡単なものであればあるほど、マジシャンには高度のテクニックが要求され、そしてそうしたものほど実際に演じられた際に観客が味わうセンスオブワンダーは大きいのだ。
ロジックを理解するだけでなく、テクニックを磨く必要がある。
彼は家に帰って鏡の前でテクニックを磨くようになった。
自分の手の動きを客観的に観察するようになった。
テクニックとは言ってもたんに手先の器用さだけが重要なわけではなかった。
現在までに考案されている千種類を越える数の奇術の内で、手先の器用さが必要なトリックは、二百種類にも満たない。
もっとも重要なのはミスディレクション、誤誘導と呼ばれる技術だ。
例えば観客を右手に注目させたくない場面があれば、左手を少し前に出し、自分の視線を左手に注ぎ、右手の人指し指で何気に左手を指せばよい。
この「前に出し」「視線を注ぎ」「何気に指」す、一連の行為によって自然に客の目は左手に集まることになる。
こうした一連の行為が、ミスディレクションを引き起こしている。
ミスディレクションは、奇術だけでなく、推理小説を書く時の基本でもある。
「消防署から来ました」でなく、「消防署の方から来ました」と言って不正に消化器を売り付ける詐欺師も、言葉によってミスディレクションを演出している。
そのトリックに最適なミスディレクションは、トリックを隠ぺいするだけでなく、奇術の効果をより高めるためにもっとも重要なテクニックなのだ。
ロジックを理解し、ハンドテクニックを身に付け、ミスディレクションの重要性を知った彼はようやく一人前のマジシャンになった。
そんな彼がある時、いきなり麻雀打ちになってしまった。
麻雀打ちになった経緯にもいろいろとあるのだが、問題にすべきは、マジシャンが麻雀打ちになったそのことにつきる。
マジシャンといい麻雀打ちとはいっても、どちらもアマチュアではあるのだが、一般的な愛好者の中でもかなり高いレベルに彼は位置していたように思われる。
麻雀打ちである彼にとって、マジシャンとして持っている技術を活かす場面はイカサマだけだったが、不思議なことに彼は手先の器用さやミスディレクションを使ってイカサマをすることはほとんどなかった。
実は不思議なことでもなんでもなく、彼は意識してそれを使わなかっただけのことだ。
麻雀をしている時にマジシャンとしての腕を披露できる場面は数限りなくあったが、そうすることを麻雀打ちとしての彼が否定していたし、またマジシャンとしての彼も他人にセンスオブワンダーを味わってもらえない限り奇術を演じる意味を見出せなかった。
麻雀打ちである彼は、マジシャンである彼とは同一であることはなかった。
彼は自分がマジシャンであり、麻雀打ちであることを回りの人々に隠すことはしなかった。
履歴書の趣味特技欄には「どちらも趣味でなく特技です」との一文まで付け加えることもあった。
やましいことなんて何もないので、隠す必要はないと思ったのだ。
ところが、麻雀をしない人にとっては、麻雀と奇術を結び付けるものはイカサマしかなかった。
「手先が器用だから、麻雀も強いんでしょうね」
手先が器用なんて言い方はマジシャンには相当失礼なだけでなく、だから麻雀が強いなんて麻雀打ちにとっては侮辱である。
そんな言い方をされるのは決まって、麻雀とは関係のない場所での食事後の雑談であったり、会議の休憩中であったりするので、むきになって否定するのもおとな気なく、ただ曖昧に笑ってごまかすだけだ。
全然、イカサマなんてやったことがない、と言い切れないことがもどかしくもあるが、それは麻雀を覚え立ての頃、学生の時分に不完全な元禄積みをやったことがあるくらいであり、手積みの当時は誰にでも経験があることなので今となっては時効であるどころか、古き良き時代の昔話の一つにしてしまっても問題のないことなのだ。
だが、マジシャンでもある彼には、マジシャンであることの負い目があるのも話を複雑にしている要因だ。
そうでない人には信じられないことだが、世の中のマジシャンの全員が、自らの職業や趣味や特技、つまり奇術をする自分に、ある意味でたいへんな負い目を持っているのだ。
彼らが身に付けたミスディレクションを駆使する技術とは、言い換えれば、人を欺く技術である。
東急ハンズで、何か新しいネタはないものかと目をこらしている時の彼らは、同時に、どうやって人を騙そうかと考えているのである。
古今東西の詐欺の手口を知り抜き、超常現象の裏事情にも詳しい彼らが唯一信奉する宗教は「科学」であり、占いや姓名判断や死後の世界なんてものには目もくれずに、ただ、どうやって人を騙そうか欺こうかということにばかり意識を集中している毎日なのだ。
本当の目的は、人々にセンスオブワンダーを味あわせること、驚かすことであるのに、その手段としてやっていることは、あまり道徳的とはいえないことなのである。
彼もまた、イカサマなんてとんでもない、とは声を大にして言えないのだ。
マジシャンとしての彼はイカサマばかりやっているのである。
麻雀文化の中で、イカサマという行為は一つの無視できないトピックスではあるが、麻雀そのものが大好きな彼は、無意識の内にその存在を忘れようとしているようだ。
積み込み、拾い、すり替え、通し、どれも得意なはずのマジシャンの彼は、麻雀打ちとしての自分に、よけいな気をつかわせてすまないな、といつも思っている。
ではあるけど、マジシャンの彼はたまに点棒を眼球に突き刺したり、牌を飲み込んだりすることがあって、麻雀打ちとしての彼の機嫌を損ねていたりもする。
マジシャンは懲りないのである。
彼が牌を飲み込むことを聞いたある人から質問されたことがある。
飲み込んだ牌は、当然、吐き出すこともできるんですよね?
牌を吐き出す、スゴイですね。
でもどうせなら、牌じゃなくって、点棒を吐き出してください。
...。